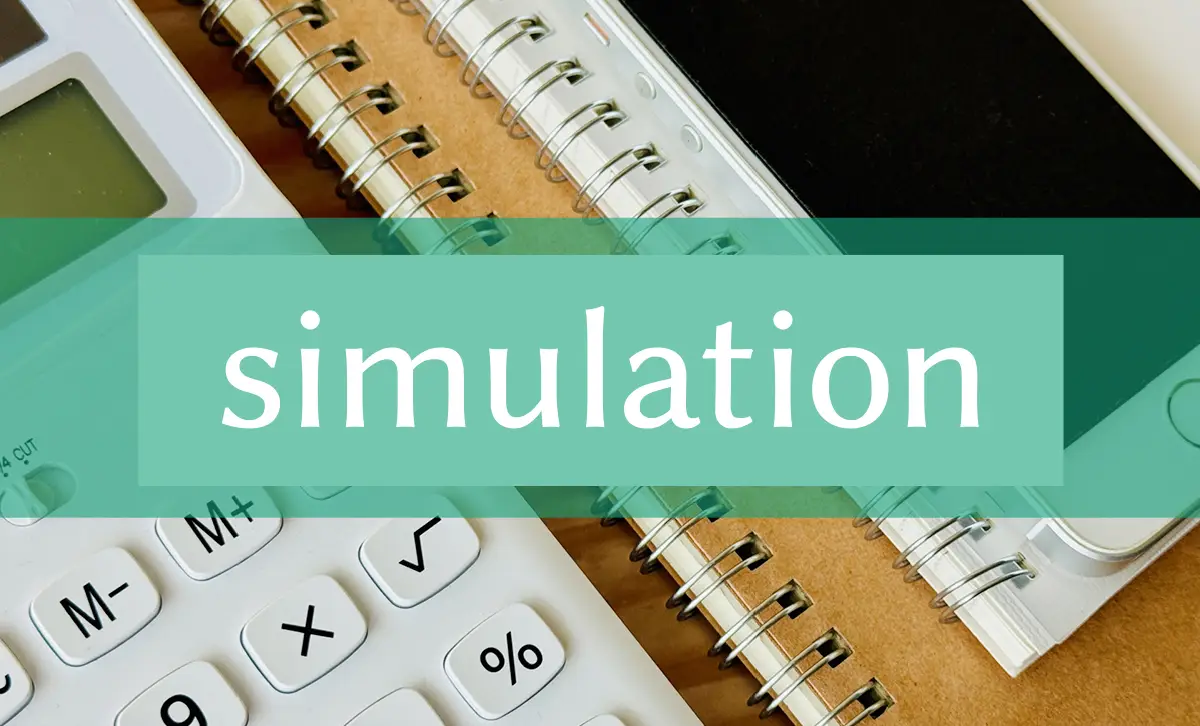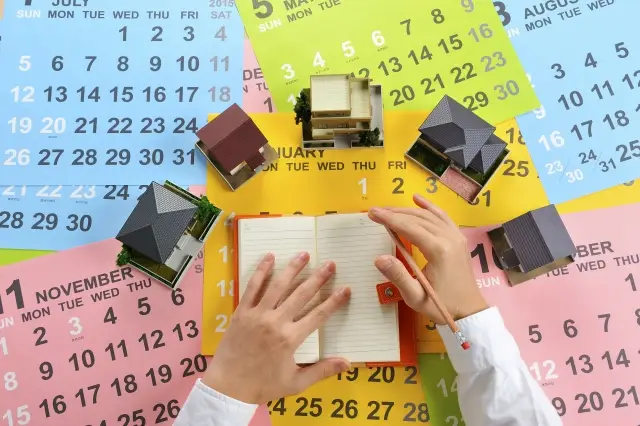不動産売却の手数料、いくらかかる?相場から内訳まで丸わかり!

不動産を売却するときには、「手数料」が必ずといってよいほど発生します。特に不動産会社に仲介を依頼する場合、「仲介手数料」という形で費用を支払うのが一般的です。
ただし、「なぜ手数料が必要なのか?」「いつ支払うのか?」「いくらが相場なのか?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。さらに2025年現在、不動産売却をめぐる制度や特例も整備されており、過去の情報のままでは正しい判断ができない可能性があります。
この記事では、不動産売却時の手数料の仕組み・相場・節約方法・注意点を、2025年最新の制度を踏まえてわかりやすく解説します。
入力はカンタン1分!24時間受付中
不動産売却時の手数料とは?

不動産会社の仲介を通して不動産を売却するときは、仲介手数料を支払う必要があります。
そもそも、なぜ不動産売却の際は手数料が必要になるのでしょうか。まずは、手数料の基本的な知識を身につけていきましょう。
不動産売却時に手数料を支払う理由
不動産売却時に支払う手数料は、「仲介手数料」と呼ばれています。仲介手数料は、物件の売買契約が成立したとき、仲介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。
不動産会社が担う業務は多岐にわたります。たとえば、
- 物件の調査・査定
- 不動産ポータルサイトや広告への掲載
- 内覧の案内や交渉
- 契約書や重要事項説明書の作成
- 引き渡しまでの手続きサポート
手数料は成功報酬なので、 売買が成立しない場合は不要となることが一般的です。
なお、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」や、個人間で売買を行う場合には、 仲介手数料は発生しないのが通常です。
不動産売却の手数料を支払いのタイミング・支払う人
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で支払い義務が発生します。宅地建物取引業法により、契約前に手数料を請求することは禁止されているため、安心してください。
不動産会社ごとの方針によって変わりますが、支払い方法は大きく2つに分かれます。
契約締結時と引き渡し時に分割して支払う(半金ずつ)
引き渡し時に全額支払う
また、手数料を支払うのは売主・買主の両方です。双方が不動産会社に仲介を依頼した場合、それぞれから手数料を受け取ることを「両手取引」といいます。
売買が成立しなくても手数料が必要なケース
原則として、売買契約が成立しない限り手数料は不要です。しかし例外的に、契約成立後に解除となった場合には、仲介手数料を支払う必要が出てきます。
代表的なケースは以下のとおりです。
- 手付解除:契約後、売主または買主が手付金を放棄または返還して解除する場合
- 違約解除:売買代金未払いなど契約違反によって解除する場合
- 合意解除:売主・買主双方が合意のうえで契約を解除する場合
これらは契約当事者の事情によって契約が解除されるため、不動産会社に仲介手数料の請求権が認めらます。一方で、「住宅ローン審査が通らなかった」「契約者に判断能力がなかった」などの契約者の責めに帰さない理由による解除では手数料は発生しません。
契約解除時の取り扱いについては、媒介契約書に詳細が記載されているため、署名押印前に必ず内容を確認しておきましょう。
不動産売却の手数料はいくらが目安?

不動産売却時にかかる手数料は、どれくらいの金額が目安になるのでしょうか。
ここでは、手数料の具体的な金額について詳しくみていきましょう。
不動産売却時に支払う手数料の上限額
仲介手数料には法律で上限が定められており、これが実質的な相場となっています。
成約価格ごとの手数料上限額は、表のとおりです。
【宅地建物取引業法による上限額】
| 成約価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買代金の5.5% |
| 200万円超~400万円以下 | 売買代金の4.4% |
| 400万円超 | 売買代金の3.3% |
※上記には消費税10%が加算されます
※出典:国土交通省|宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
上記の表を用いる場合、それぞれの区分ごとに計算し、最後にすべてを合算した額を算出することになります。しかしこの方法では手間がかかるので、一般的には速算式が使われます。
400万円超の場合
(売却価格 × 3% + 6万円)+消費税200万円超~400万円以下の場合
(売却価格 × 4% + 2万円)+消費税200万円以下の場合
(売却価格 × 5%)+消費税
速算式で使用される「2万円」や「6万円」という金額は、仲介手数料の計算を簡略化するための調整額です。計算の際は、 どちらの式を使用しても問題ありません。
手数料の計算例(成約額1000万円の物件)
【速算式を使わない場合】
400万円超の部分:200万円×5.5%=11万円
200万円超~400万円以下の部分=200万円×4.4%=8万8,000円
400万円を超える部分=600万円×3.3%=19万8,000円
合計:39万6,000円
【速算式を使う場合】
成約価格が400万円超の場合
=(1,000万円×3%+6万円)+消費税10%=39万6,000円
速算式を使った方がシンプルな計算で手数料を計算できます。速算式を使っても手数料の上限に差額は生じないので、安心してください☺
【成約価格別】手数料の早見表
ここでは、成約価格別に手数料の金額をまとめた早見表を紹介します。
成約価格 | 手数料の上限 |
100万円 | 5万5,000円 |
500万円 | 23万1,000円 |
1,000万円 | 39万6,000円 |
1,500万円 | 56万1,000円 |
2,000万円 | 72万6,000円 |
3,000万円 | 105万6,000円 |
4,000万円 | 138万6,000円 |
5,000万円 | 171万6,000円 |
不動産売却の手数料を節約する方法

仲介手数料は、不動産売却にかかる諸費用のうち大きな割合を占めます。そのため、できるだけ節約したいと考える方は多いかもしれません。節約したい場合、次の方法があります。
手数料の割引交渉をする
不動産会社のなかには、交渉をすれば手数料を割引してくれるところもあります。思い切って相談してみることもひとつの手です。
ただし、仲介手数料は売却活動に必要な費用です。 無理に割引してもらうと、熱心に売却活動をしてくれなくなるおそれがあります。
手数料の値引きをお願いする場合、1社のみに仲介を依頼する「専属専任媒介契約」が有効なケースがあります。専属専任媒介契約を締結すれば、必ず自社を通じて取引してもらえるという安心材料を与えられるためです。
ただし、専属専任媒介契約には「囲い込み」のリスクがあります。囲い込みとは、故意に売却活動を制限して自社のみで売買取引を完結させることで、両手取引を実現しようとする手法です。その場合、売却に時間がかかったり売却価格が安くなったりする可能性があります。
リスクを負ってまで割引を交渉すべきか、慎重に検討することが大切です。
不動産の売却と購入を同じ会社に任せる
不動産売却にともなって購入も検討している場合は、同じ不動産会社に仲介を依頼することで、手数料を割引してもらえるケースがあります。不動産会社によって値引きに応じてくれるかは変わってくるので、必ず成功するとは限りませんので、一度相談してみるとよいでしょう。
買取・個人売買にする
不動産会社に直接物件を買い取ってもらう場合や、個人間で売買する場合は、仲介手数料は発生しません。買い取ってくれる不動産会社や知人に心当たりがあれば、検討してみてもよいでしょう。
関連記事:不動産買取とは?仲介との7つの違いやメリット・デメリットを解説
ただし、買取や個人売買の場合は、 希望する買取価格がつかない可能性があります。また、個人売買では契約関係の手続きをご自身で行うことになるため、トラブルのリスクが高まる点に気をつけましょう。
不動産売却時にかかる諸費用の内訳

一般的に不動産売却の際は、手数料以外にも以下のような諸費用がかかります。
印紙税
登記費用(抵当権抹消登記など)
譲渡所得税・住民税
住宅ローン返済手数料
測量費・解体費・ハウスクリーニング費など
手数料と諸費用の合計額は、成約価格の4~6%程度が目安です。どのような費用が含まれるのか、内訳と金額の相場をみていきましょう。
関連記事:不動産売却での経費は?確定申告で節税できる項目とできない項目を解説
印紙税
売買契約を締結するときは、経済的取引に関連する書類に対して課される「印紙税」を収める必要があります。
※出典:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
なお、 契約書を2部作成する場合は、印紙税も2部分必要になります。印紙税を収めない場合、過怠税が課されるため注意しましょう。
登記費用
不動産売却の際は、次の2つの登記手続きが必要になります。
抵当権抹消登記
所有権移転登記
抵当権抹消登記は、借りていた住宅ローンを全額返済し、金融機関が設定していた抵当権を抹消するための手続きです。登録免許税と司法書士への報酬をあわせると、およそ2~3万円の費用がかかります。
ご自身で手続きして費用を節約することも可能ですが、専門的な書類の作成が必要になるため、司法書士に一任することが一般的です。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た場合は、その金額に応じて税金がかかります。
譲渡所得が発生したかどうかは、次のように計算します。
譲渡所得額=不動産の売却価格–(取得費+譲渡費用)-特別控除額
不動産を売却した金額から、不動産を入手するためにかかった費用と売却にかかった諸費用を差し引ける点が特徴的です。 取得額や譲渡費用を差し引いて利益が出なかったときは、税金は発生しません。
譲渡所得がプラスになった場合は、次の税率をかけて譲渡所得税と住民税を算出します。
所有期間 | 税率 | |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 39%(所得税 30%+住民税 9%) |
長期譲渡所得 | 5年超 | 20%(所得税 15%+住民税 5%) |
※令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税とあわせて申告・納付する
※出典:国税庁|No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
上記のように、不動産を所有していた期間に応じて税率が変わる点に注意しましょう。
住宅ローン返済手数料
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、一括返済の事務手数料が発生します。
例えば、りそな銀行の場合は、契約に応じて1万1,000~3万3,000円の手数料がかかります。一方で、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」の場合は、全額繰り上げ返済の手数料はかかりません。
詳細な金額は金融機関によって異なるので、早めに確認しておくことを推奨します。
※参考:りそな銀行|住宅ローンの手数料・諸費用
フラット35|繰上返済
その他の費用
不動産や売主の状況によっては、ここまでに紹介した種類以外の費用が発生することもあります。
代表的な費用の種類は、次のとおりです。
ハウスクリーニング費用
測量費用
解体費用
引っ越し費用
書類の発行手数料 など
まとまった費用が必要になることもあるため、事前に資金計画を立てておくことが大切です。特に買い替えを検討している方は、資金不足にならないよう気をつけましょう。
不動産売却の手数料に関する注意点
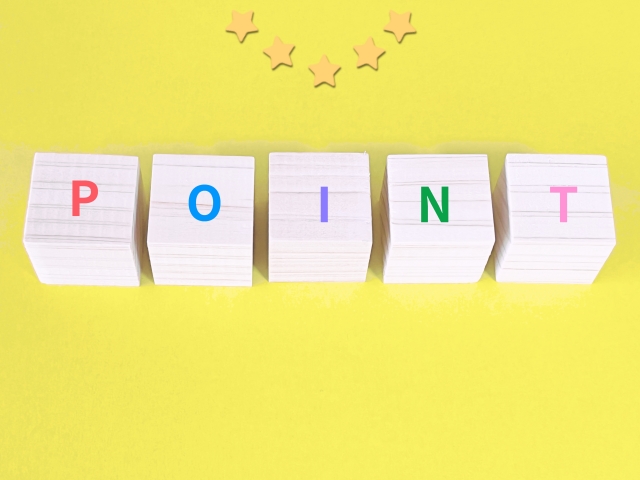
関連記事:不動産売却の注意点を徹底解説|売却前・契約時に気をつけたいポイントとは?
特別な依頼は別途手数料が必要
基本的に、売却活動にかかる業務に対する費用は仲介手数料に含まれています。しかし、売主の希望で特別な対応をしてもらったときは、別途手数料を請求されることがあることを押さえておきましょう。ただし、 追加費用の請求については事前の説明や合意が必要です。事前告知なしで請求されることはありません。
手数料の安さだけで不動産会社を選ばない
仲介を依頼する不動産会社を選ぶときは、手数料の安さだけで判断してはいけません。あまりにも手数料が安い場合は、その理由を聞いてから判断するようにしてください。
なかには、手数料を安くする代わりに売却活動や契約手続き、サポートなどの対応品質を下げている業者も存在しています。そのような業者はごく一部ですが、 トラブルを防いで気持ちよく契約を締結するためにも、手数料の金額に惑わされずに業者選びをすることが大切です。
仲介手数料には消費税がかかる
個人が所有する不動産(土地・建物)の売却代金は非課税ですが、不動産会社に支払う手数料は課税されます。混同しないように気をつけましょう。なお、同じ不動産売却であっても「法人が所有する建物」を売却するときは課税対象になります。
低廉な空き家等の売却は手数料が増額される
「低廉な空き家等」とは、具体的に400万円未満の空き家などの不動産です。価格が安い不動産を売却するときは、手数料の上限が増額される特例が適用されます。
平成30年1月1日に施行された告示で、400万円未満の不動産の売買を仲介した場合、最大19万8,000円の手数料を受け取れることが決定されました。ここには、手数料の他に不動産の調査費用相当額(人件費)も含まれます。
例えば、従来であれば200万円の物件を売却した際、不動産業者が受け取れる仲介手数料は11万円でした。しかし、この特例が適用されることにより、最大8万8,000円を加算した19万8,000円が受け取れるようになるのです。
不動産業者にとっては、どのような物件であっても売却活動の内容は大きく変わらない一方で、物件価格が安い場合は受け取れる手数料が大幅に減ってしまいます。
この矛盾と空き家問題を解消するために、「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」(最大19万8,000円まで可)は2025年も有効であり、地方の空き家問題の解決策として活用されています。なお、 手数料が増額されるのは売主だけなので、買主は従来どおりの手数料額が上限となります。
※参考:公益財団法人 不動産流通推進センター|低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例
不動産会社の選び方
不動産会社を選ぶ際は「手数料の安さ」だけでなく、実績・対応力・信頼性を重視することが大切です。ご自身の状況をどう汲み取ってもらえるか、回答はスムーズか、営業や会社との「波長」も大事な事項だと思います。
もし「手数料をかけずにスムーズに売却したい」とお考えなら、不動産会社による直接買取も選択肢に入れてみてください。
不動産買取なら「新潟・長岡・上越不動産買取応援隊」へ
当社「新潟・長岡・上越の不動産買取応援隊」では、仲介を介さない直接買取を行っています。そのため、仲介手数料は一切かかりません。
査定・相談は無料
相続や住み替えのサポートも可能
即現金化でスピーディーな取引
不動産売却における「手数料」を節約しながら、安心できる取引を実現したい方は、ぜひ当社に一度ご相談ください!
経験豊富なスタッフが、お悩みに合わせた解決方法をご提案いたします!また、相場データに基づいた適正な価格を提示し、スピーディーかつ安心できる売却を全力でサポートいたします!
入力はカンタン1分!24時間受付中

新潟県の不動産に精通している、査定/買取・買取専門スタッフが記事を監修しています。不動産の査定や買取について、いつでもお気軽にご相談ください。