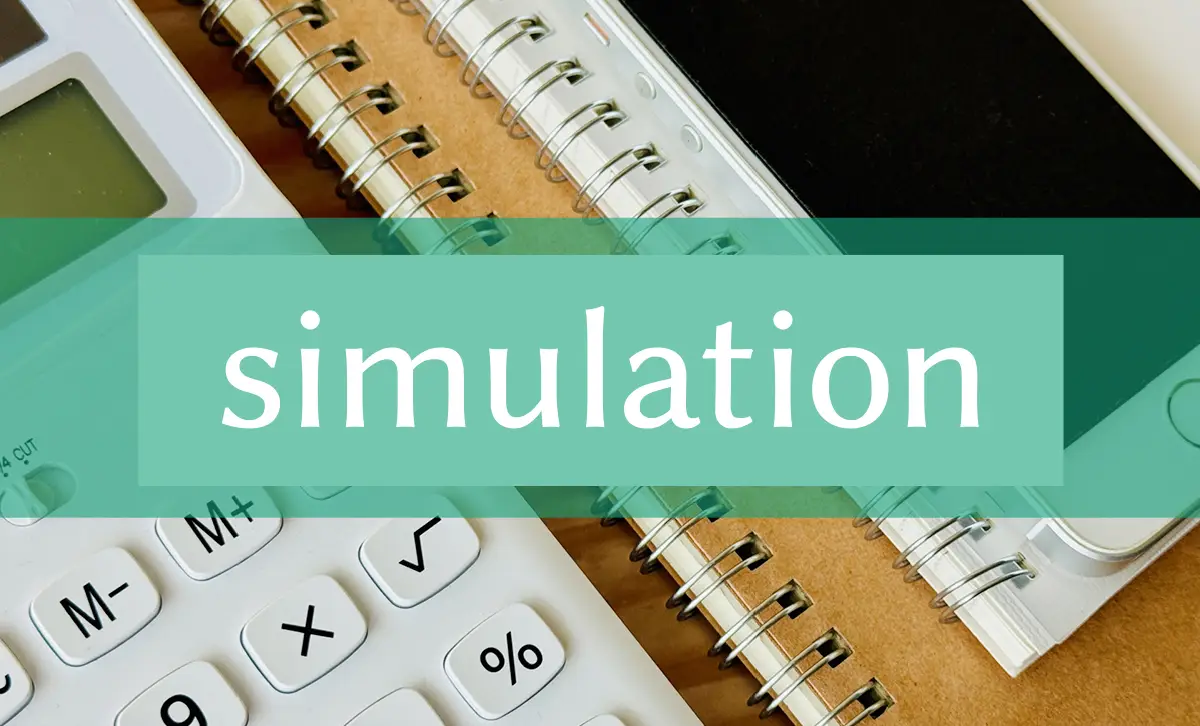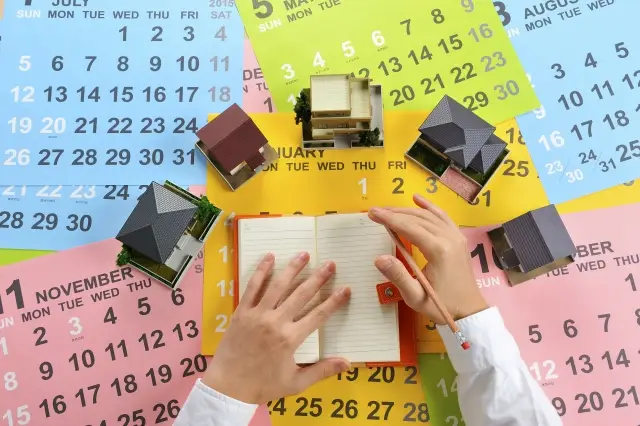いらない田舎の土地を処分する方法9選【2025年版】|放置するリスクも解説

田舎に土地を所有しているものの、遠方で管理が難しくお困りではないですか?
本記事では、いらない土地をお持ちの方にお勧めする9つの方法と、放置するリスクについて詳しく解説します。土地の状況に応じた最適な方法を紹介しますので、不要な空き地の有効活用や処分をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
田舎のいらない土地を処分する方法9選│売れない理由~対策まで解説

「田舎の土地を相続したけれど、使い道がない」「草刈りや固定資産税が負担に…」「誰か買ってくれないかな?」
そんなお悩み、実はあなただけではありません。
全国的に“いらない土地”に関する相談が年々増えています。この記事では、使っていない田舎の土地を手放したい方に向けて、具体的な処分方法をご紹介します。
大切なのは、「売れない」と思い込まず、適切な方法で行動を起こすことです。
なぜ田舎の土地は手放しづらいのか?
都市部と比べて、田舎の土地には以下のような理由で買い手がつきにくいケースがあります。
周囲に住宅や商業施設が少ない
インフラ(上下水道、ガスなど)の整備がされていない
土地が広すぎる/狭すぎる
接道義務を満たしていない
地目が山林・畑・原野などで再利用しづらい
相続登記がされていない
こうした要因があっても、「処分できない土地」ではありません。
いくつかの方法を知っておくことで、スムーズな手放しが可能になります。
売却による処分
まずは、最も一般的な売却による処分方法から紹介します。土地の売却をしたことがなくても、専門家の助けを得ることでスムーズな売却が可能です。
以下、主な売却先をみていきましょう。
1.不動産会社に依頼して売却する
最も一般的で安心なのが不動産会社を通じた売却です。売買契約や価格査定など、複雑な手続きを専門家がサポートしてくれるため、不動産の知識がない方にも向いています。
✅こんな方におすすめ
相場に近い価格で売却したい
売買の手続きを任せたい
離れた場所に住んでいて現地に行けない
【ポイント】
スピーディーな売却を希望する場合は、不動産の「買取」も検討しましょう。価格は下がりますが、確実に現金化できます。
仲介・買取ともに、土地の価値を最大限に引き出すためには、土地の特徴や地域性を理解している地元の不動産会社に依頼することが重要です。複数の不動産会社に相見積もりを依頼し、条件に合致する会社を選定しましょう。
関連記事:土地売却の流れを6ステップで解説|費用や税金、必要書類、注意点も
関連記事:土地買取の進め方は?流れ・メリットから高く売るコツ、業者の選び方まで解説
2.隣地所有者に売却する
隣接地の所有者に売却する方法もおすすめです。隣地の方にとっては土地の拡張となるため、好条件での売却が見込めます。
✅交渉の進め方
登記簿謄本で所有者を確認
自治会や不動産業者などを通じて間接的に打診
農地の場合は農業委員会の許可が必要
※直接交渉は避け、第三者を介して話を進めることでスムーズな取引につながるでしょう。
※農地の場合は農地法の制限があるため、農業委員会への許可申請が必要となる場合も。事前に必要な手続きを確認し、計画的に進めていくことが大切です。
3.自治体に売却する
道路拡張や公園整備など、公共の目的で使用される可能性がある土地であれば、自治体が買い取ってくれる場合があります。自治体が買い取る場合は適正価格での取引が期待でき、手続きも確実です。
ただし自治体が土地を必要としている場合に限られるため、売却できる機会は限定的となります。まずはお住まいの市区町村の担当窓口(一般的に宅地課)に相談してみると良いでしょう。都市計画などの将来的な開発計画に合致する場合は、検討の余地があるかもしれません。
無償での処分
売却が難しい土地の場合、無償での処分方法も検討する価値があります。特に維持管理費用が土地の価値を上回るような場合や、相続で取得した土地の処分を考えている場合に有効な選択肢です。
無償での処分方法について、それぞれの特徴と手続きを解説します。
4.自治体に寄付する
自治体への土地寄付は、公共の利益に適う場合に限り受け入れられる可能性があります。ただし自治体は管理コストが発生する土地の受け入れには慎重な姿勢を示すことが一般的です。
以下は、寄付が受け入れられやすい土地の条件です。
✅受け入れられやすいケース
公共施設や公園に隣接している
公園や道路用地として活用可能な場所
防災・文化財保護に活用できる土地
一定のインフラ条件を満たしている
【注目】
2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」では、一定条件を満たせば手数料を支払い国に土地を引き取ってもらえます。※2025年現在も制度継続中(手数料10万~30万円程度)
5.相続放棄する
相続放棄とは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述することで、土地を含むすべての相続財産を放棄できる方法です。特に相続財産に多額の負債が含まれている場合や、相続争いを避けたい場合に有効な選択肢となります。
✅注意点
土地だけでなくすべての相続財産を放棄することになる
一度放棄すると撤回できない
相続後の放棄(放置)は原則できない
すでに相続を承認してしまった場合や期限を過ぎた場合は相続放棄ができないことも理解しておきましょう。
活用による処分
すぐに売却や寄付が難しい土地でも、活用することで収益を得ながら将来的な処分の機会を待つことができます。
6.貸土地として活用する
土地を貸すことで、定期的な収入を得ることが可能です。
✅代表的な貸し方
駐車場 |
|
資材置き場 |
|
農地 |
|
土地を貸し出す前には、必ず土地の権利関係や法的な利用制限を確認しましょう。また固定資産税の支払い状況や近隣住民への配慮事項も事前に確認し、トラブルを防ぐことが大切です。
7.事業として活用する
田舎の土地でも、地域特性を活かした事業展開により収益を生み出すことが可能です。
低コストで始められる事業 |
|
中規模の投資で始められる事業 |
|
大規模投資が必要な事業 |
|
事業による活用は、将来的な売却や相続も見据えた土地の価値向上につながる可能性があります。専門家に相談しながら、慎重に検討を進めましょう。
行政サービスを活用した処分
土地の処分に悩んでいる方のために、行政が提供している便利なサービスがあります。これらのサービスを活用することで、新しい所有者を見つけやすくなります。特に田舎の土地は、行政サービスを利用することで、移住希望者とのマッチングが期待できます。
8.空き家・空き地バンクに登録する
空き家・空き地バンクは、自治体が運営する土地や建物の売買・賃貸のマッチングサービスです。地域の活性化を目的としており、田舎へ移住を希望する方々への情報提供の場として多くの自治体が運営しています。
空き地・空き家バンクに登録する条件は以下のとおりです。
- 対象となる自治体のエリア内にある土地であること
- 不動産会社との媒介契約が結ばれていないこと
- 法令違反がないこと
地方への移住ニーズの高まりを受け、空き家・空き地バンクへの登録は、土地処分の有効な選択肢の一つといえるでしょう。
参考:建設産業・不動産業:空き家・空き地バンク総合情報ページ - 国土交通省
9.農地バンクに登録する
農地バンクは、農林水産省が推進する農地の貸し借りをサポートする制度です。農地中間管理機構が仲介役となり、所有する農地を担い手に貸し付けることができます。
✅メリット
- 固定資産税と都市計画税が3年間減税される場合がある
- 賃料の未払いリスクがない
- 契約手続きが簡素化される
- 遊休農地の有効活用ができる
近年では所有者不明農地や遊休農地も対象となっています。これにより、これまで活用が難しかった農地でも、農地バンクを通じて新たな担い手に貸し付けることが可能になりました。
なお、農地バンクに登録できない場合もあります。例えば、転用目的と認められる場合や農地法に違反している場合、所有権以外の権利が設定されている場合などは登録が認められません。農地バンクへの登録を検討する際は、まずは地域の農地中間管理機構に相談しましょう。
どうなる?不要な土地を放置するリスク

不要な土地を空き地としてそのままにしておくと、以下のような問題が起きる可能性があります。
維持費の負担
いらない田舎の土地を放置するリスクとして、固定資産税などの費用がかかることが挙げられます。また市街化区域内の土地では、都市計画税も追加で課税されていきます。これらの税金は、土地を所有している限り避けることができません。
特に注意が必要なのは、土地が「特定空家等」に指定された場合です。この場合、固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がることも。また自治体から改善命令が出された場合、強制的な整備費用を請求されることもあり得るでしょう。
このように、土地を放置しているだけでも予想以上の費用負担が発生します。土地の価値と比較して維持費が見合わない場合は、早めの処分を検討することをおすすめします。
近隣トラブルの発生
管理されていない土地は、周辺住民とのトラブルの原因となりやすいものです。特に雑草の繁茂による害虫の発生や、不法投棄の問題が深刻となっています。
このような状況が続くと、自治体による指導や是正勧告などの行政処分を受けることもあり得るでしょう。土地所有者の社会的責任として、適切な管理を行うことが求められています。
不法侵入・放火のリスク
管理が行き届いていない空き地は、防犯上の問題を引き起こす可能性があります。特に人目につきにくい場所では、不法侵入や放火など犯罪の標的となりやすいです。
万が一、不法侵入者が事故に遭った場合、土地所有者が管理責任を問われる可能性も。また、放火などによって近隣に被害が及んだ場合、損害賠償を請求される事態も想定されます。
このような事態を防ぐためには、定期的な見回りやフェンスの設置、防犯カメラの導入など、適切な管理体制を整えることが欠かせません。土地の管理を放棄することは、予期せぬ法的責任や経済的負担を招く可能性があることを認識しておく必要があります。
将来的な処分費用の増加
土地を放置し続けることで、将来的な処分費用が増大することも大きなリスクです。特に田舎の土地は、時間が経てば経つほど価値が下がる傾向にあります。
さらに、相続が発生した際の問題も考えられます。相続人の特定や権利関係の整理に費用がかかるだけでなく、相続税の支払いも必要となる可能性があります。特に、相続人が複数いる場合は、権利関係の整理に多額の費用が必要となることも予想されます。
このように、土地を放置することで将来的な負担は確実に増加していきます。これらの費用を最小限に抑えるためにも、早めに処分や活用の方法を検討することが大切です。
まとめ:田舎の土地は「早めの対策」がカギ!
いらない土地の買取相談なら「新潟・長岡・上越不動産買取応援隊」へ!

売却も、活用も、相続のご相談も。
地域密着20年超の実績を持つ不動産買取専門の私たちが、親身に対応いたします。
新潟・長岡・上越で自宅売却を検討している方は、ぜひ地域密着の 「不動産買取応援隊」 にご相談ください。
- 仲介手数料無料
- 地域密着20年超
- 全国24店舗のネットワーク
経験豊富なスタッフが、お悩みに合わせた解決方法をご提案いたします!また、相場データに基づいた適正な価格を提示し、スピーディーかつ安心できる売却を全力でサポートいたします!
入力はカンタン1分!24時間受付中

新潟県の不動産に精通している、査定/買取・買取専門スタッフが記事を監修しています。不動産の査定や買取について、いつでもお気軽にご相談ください。